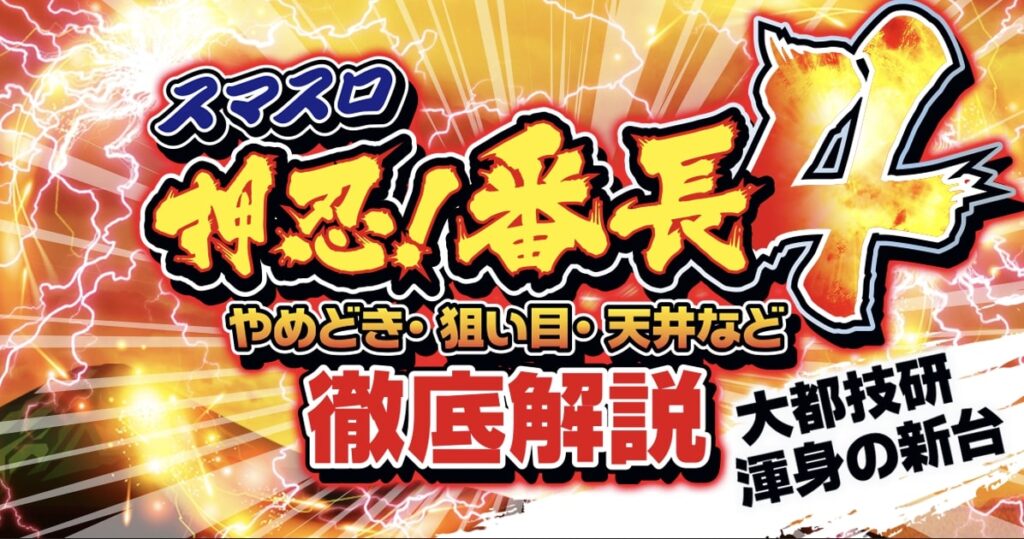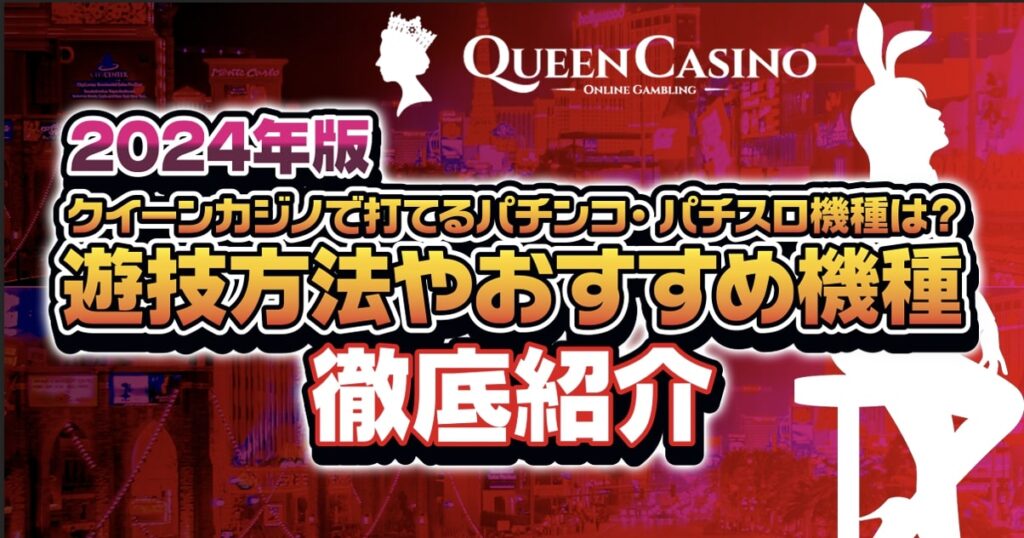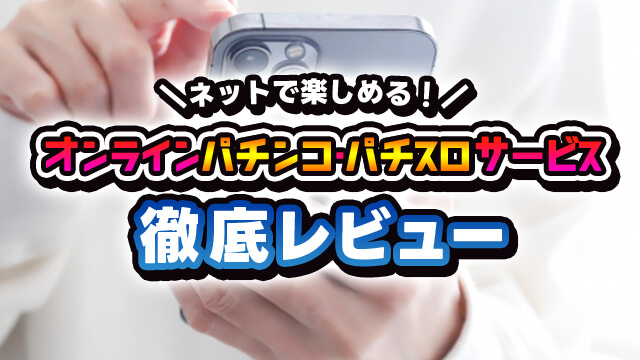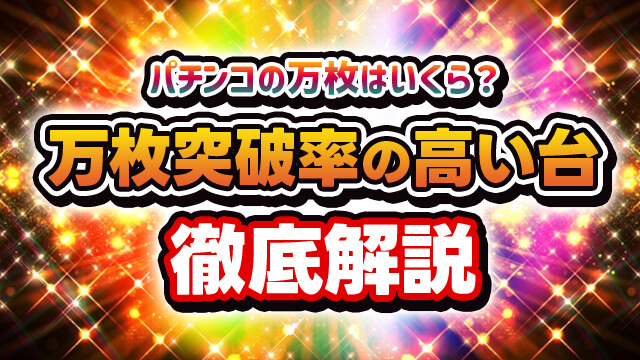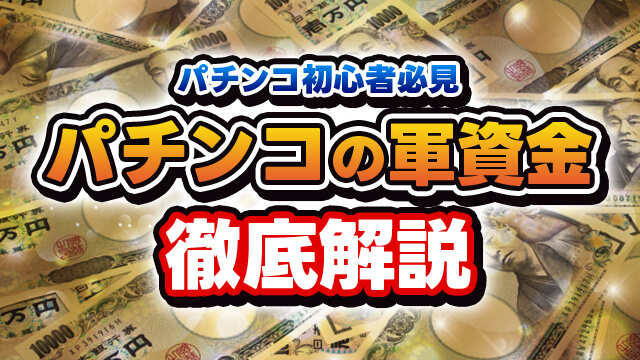-

スマスロ 押忍!番長4 やめどき・狙い目・天井などを徹底解説【大都技研渾身の新台】
大都技研の新台スロット「L押忍!番長4」がついに導入開始されます。 番長シリーズといえば、初代から数多くファンに愛されているメーカーオリジナルシリーズです。 もちろん、筆者も大ファンの1人です。 そんな今まで長年愛されてきた番長シリーズの正統... -

クイーンカジノで打てるパチンコ・パチスロ機種は?遊戯方法やおすすめ機種を紹介【2024年】
クイーンカジノは、パチンコ・パチスロがスマホ・PCで気軽に打てるということで話題を集めているオンラインカジノです。 777Realなどパチンコ・パチスロが打てるアプリやサービスはあるものの、娯楽目的で現金遊戯をすることはできません。 しかし、クイー... -

パチンコの羽根モノってどんな台?仕組みは?現行のおすすめ羽根モノ機種も紹介
パチンコ屋には、常時100種類以上の台が設置されていることがほとんどです。 その中でも9割以上は、デジパチと呼ばれるヘソに玉が入った時点で抽選が開始し、当落が決まるタイプの機種です。 そして残りの数%ほどの台は羽根モノと呼ばれる機種です。 羽根... -

スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ解説 / 天井・立ち回り・やめどき・設定示唆などを紹介
2024年の2月にあのコードギアスがスマスロで導入されました。 導入されたばかりということもあり、 『コードギアスってどんな台なの?』 『勝てる立ち回りを知りたい』 こんなお悩みの方も多いと思います。 本日は、そんな方に向けて『スマスロコードギア... -

スマスロ ゴールデンカムイ やめどき・狙い目・天井などを徹底解説【サミー期待の新台】
2024年4月にサミーからTVアニメの『ゴールデンカムイ』のスマスロ『Lゴールデンカムイ』が導入されました。 疑似ボーナスからのAT突入を目指し、さらにATでの獲得枚数が増えると上位ATに突入するスマスロならではの爆発力も兼ね備えています。 基本的には... -

【オンラインパチンコ】パチンコ・パチスロをPCで打てるサービスを紹介 / 現金遊戯と無料で遊べる両方紹介
現在、全国にあるパチンコ屋は、地域にもよりますが、23時や24時には閉店してしまいます。 しかし、パチンコやパチスロが大好きで閉店した後も打ちたい!という人も多いかと思います。 そんな方に向けて今回は、PCやスマホでパチンコが打てるサービスを紹... -

パチンコの時短とは?意味や仕組みを初心者にもわかりやすく解説
「今更だけどパチンコ用語の時短てどういう状態?』 「S Tと時短って何が違うの?」 こんな悩みはパチンコに興味はあるけど、よく分からないなんて方に多いですよね。 そんな方に向けて本日は、パチンコの『時短システム』について詳しく解説します。 知識... -

パチンコハマり確率計算ツール / 1000ハマりする確率は?
パチンコの気になるハマり確率計算シミュレーターです。 ぜひご活用ください! 【パチンコの主なハマり確率まとめ】 ここからは、計算シミュレーターを使うのがめんどくさいという方に向けて、表でまとめてみたので、ぜひ参考にしてみてください。 ミドル... -

スロットの万枚はいくら?万枚を狙える突破率の高い現行機種も紹介【2024年】
スロットを打ったことがある人なら誰しもが夢見る「万枚」。 パチスロ歴10年以上の筆者は、恥ずかしながら実はまだ万枚を出したことがありません。 5号機が撤去され、「万枚を出せる機械はなくなった」と言われたこともありました。 しかし、スマスロ第一... -

パチンコの軍資金の平均はいくら?スペックごとにおすすめの金額を伝授
パチンコを始めたばかりの初心者の方は、「パチンコで楽しむための軍資金はいくらくらいだろう」と気になっているかと思います。 パチンコの軍資金は、機種のスペック・貸玉レートによって異なります。 本記事では、パチンコを始めたばかりの初心者の方に...
12